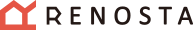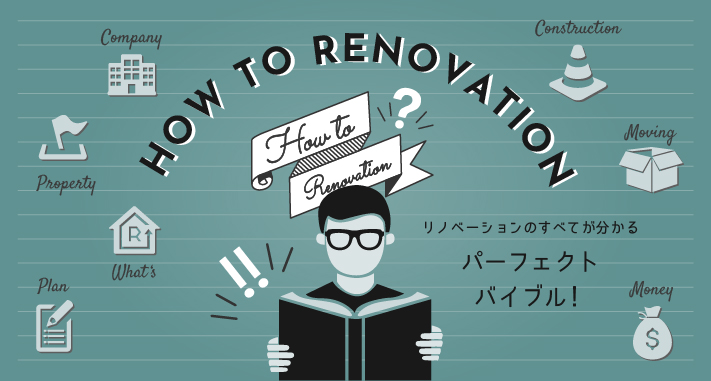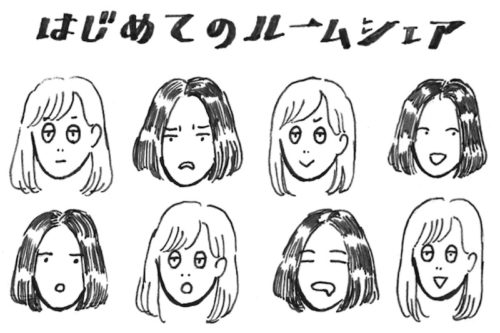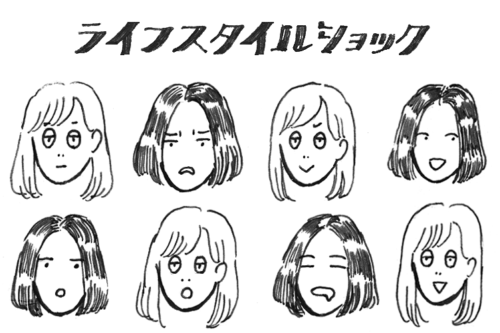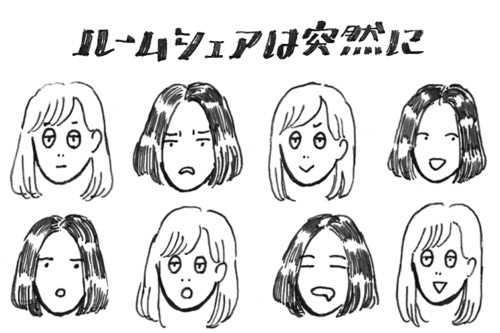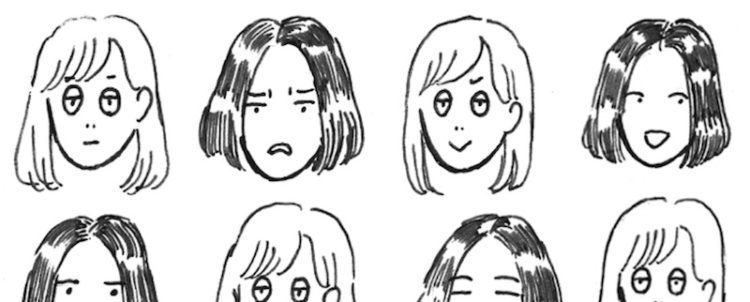「子供のようで鉅人、鉅人のようで子供」。大阪発、ハイテンションかつシュール、でも人情たっぷり。そんな独自のパフォーマンスで人気を博す劇団子供鉅人から、代表の益山貴司さん(通称:ボス)が登場! 本サイトのコラムでもお馴染みですね。
今回は弟さんたちと共同生活を送るご自宅にお邪魔して、劇団やお芝居の話を伺うだけでなく、ボス(と、その弟さん??)の個性が爆発しているお部屋の写真もパシャリパシャリと撮らせていただきました! これは必見だ!!
「王道に戻る」というトリッキーな手法。
そして2015年。満を持して、劇団は東京への移住を果たします。そこにはどんな狙いや意図があったのでしょうか。
「常に新しいことへの挑戦を続けていないと、集団として成長しなくなるし、自分たちのやっていることに飽きてしまって、興味を持つことができなくなります。僕自身が1番そうなんですが、惰性で芝居をするのがとても怖いんですよね」
チャレンジし続けること。それが子供鉅人が子供鉅人であり続けるための条件なのかもしれません。とはいえ、慣れない土地へと移り住むということ。しかも大勢の意思疎通を図りながら……。なかなか難しいのでは?
「僕が不感症なのか、楽観主義なのか……。周りが言うほど大変ではなかったですよ。東京で通用するかどうか、みたいな不安もあまりなく。というのもすでに東京での公演も何度か経験していて、我々のようなスタイルが東京ではあまり見られなくなってきているという噂も聞いていたので、ある程度はウケるだろうという計算がありました」

コラム「家をめぐる」でも紹介されたタオルかけ。 
したためた作戦表を発見しました!
「あと、僕たちは関西の演劇界の中でも『口が悪くて生意気』とか言われていたし(苦笑)、大阪でいろいろとやり尽くした感もありました。また評価されるといってもやはり関西では限界があります。
何より、当時劇団の中核を担っていた役者たちがすでに20代中盤だったし、東京に行くならそのタイミングしかなかったんです。
私は作・演出を担当しているので年齢は関係ないですけどね。ただ青春時代をつぎ込んでくれた若い役者たちのことを考えると、もうそこしかありませんでした」
一見、豪快で自由奔放な印象もあるボス。しかし時に思慮深き策士であり、またメンバー思いの良き兄貴分であろう彼の人柄が、言葉の端々に見え隠れします。

世界中に散らばっている物語を発掘するイメージで!
上京後もその勢いは止まりません。東京芸術劇場や本多劇場など、大きな劇場からのオファーがつづき、その知名度をどんどんと上げていきます。
しかし、大阪時代からつくり上げてきたイメージを覆す方向へと舵を切り始めたのも、東京進出の後のことだったようです。
「大阪では劇場以外の少し変わった場所で公演をたくさんやることで、それなりの評価を受けてきました。でもそれって 『え? こんな場所で演劇を!?』と、見る側が色メガネをかけてくれるので、それだけですでにアドバンテージがあるんですよね。入り口の時点で3割増しくらいになるというか。したがって作品自体のつくりが多少雑だったとしても成立してしまう。
もちろんそれは分かった上でやっていたことなのですが、そればかりをやっていると、当然ですが、芸は荒れてきてしまう。
そこで気づいたのは、結局は劇場でやることがもっともスリルがあるし、圧倒的に難しいということです。変な言い方なのですが、実は劇場こそが1番トリッキーなんですよね。王道に戻るのがすごく興味深く思えて」
ベーシックなフォーマットに戻って正攻法で攻めつつも、比類なきオリジナリティは残す。子供鉅人の表現は、さらに次のフェーズへと進んでいきました。

実は絵を描くのも大好き! 
洗濯は兄弟べつべつ? それとも当番制??
組織のトップとして劇団全体をマネジメントしつつ、脚本も手がけるボス。笑い、感動、シュール、エロ……と、その作品は実にカラフルで、古くからのファンにも驚きを与え続けていきます。それら物語の種をどのように生み出しているのでしょうか。
「僕の場合は、物語を生むというより “発掘する”というイメージなんです。自分の中にあるストーリーを吐き出すのではなく、世界中に転がっている物語を発掘していくわけです。例えば街角を歩いていると、知らない人が立っている。そこで『あの人は、なぜあそこに立っているのか』を考えます。すると『どういう生い立ちなんだろう』とか『今日は誰と会うんだろう』とか、どんどん物語が生まれてきますよね。
そう考えれば、街を歩いていても、他の作品をみても、素材だらけで枯渇することはありません。無限ですよね。だから、いつだって書きたいことはあります。カルマとして書くことを強制されているような感覚かな」

次の作品はどんな内容かな? 
一種のアミューズメントパークとも呼べそうな、おトイレ。
自分の周りにあるもの、すべてが物語の題材。目に飛び込むもの、耳に入るもの、すべてからインスピレーションを受け、幅広く表現をつづけていきます。
「僕は、演劇というジャンルのすべてを勝手に背負いたいんです。コメディもやる。チャンバラもやる。観客も泣かす……。そういうのが僕の気質にあっている気がします。
昔の作家さんってそうですよね。例えば黒澤明は『七人の侍』も撮れば『生きる』も撮る。そんな感じで、僕も悲劇も喜劇もぜんぶやりつくして、背負ってしまいたい。ま、だいぶかっこよく言っちゃってますけどね(笑)」
PHOTO by Kaori Nozaki
益山貴司(劇団子供鉅人)

これまで、子供鉅人のほとんど全ての作・演出を行う。
お化けと女の子に怯える幼少期を過ごした後、20世紀の終わり頃に演劇活動を開始する。作風は作品ごとに異なり、静かな会話劇からにぎやかな音楽劇までオールジャンルこなす。
一貫しているのは「人間存在の悲しみと可笑しさ」を追求することである。